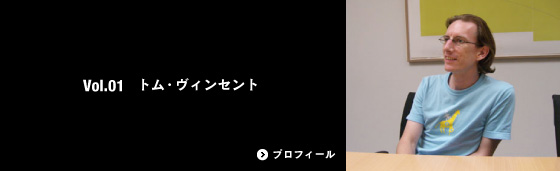
センソリウムを皮切りに、Web黎明期から日本を拠点にワールドワイドで活躍するトム・ヴィンセントさん。最近は、第1回T-1ワールドカップの初代王者や、オンラインデザインマガジン"pingmag"のディレクターとしても知られています。大学時代は演劇デザインを志していたそうですが、新しいメディアの実験精神に憧れ、アートの世界を目指していた頃に来日。その後、課題と目的が明確な「デザイン」が肌に合い、当時盛り上がり始めていたWebのデザイナーに。センソリウムのNIGHT AND DAY プロジェクトに関わったことがきっかけとなり、1999年株式会社イメージソースに入社されました。以来、日本でWebデザインに関わってきたトムさんに、インターネットとデザインの面白さについてうかがいました。
本当に見たいのは、コンテンツ。
デザインじゃない。
—最近、トムさんが特に気になるWebサイトは何ですか?
よくできているな、すごい仕事をしているな、と思うサイトはいっぱいあります。でも、本当に自分が見たいのは、デザインじゃない。コンテンツです。You Tubeサイコー!とよく思いますね。それについては、あまり詳しいことはここでは言いませんが(笑)。
私たちが作るpingmagの中でも、「私のお箸」(英語版)という、日本の箸文化をとりあげたコンテンツには、アジア中からコメントが集まりました。三軒茶屋のかき氷屋さんを特集した「町のかき氷屋さん」(英語版)には、ブラジル、パキスタン、エクアドルなどなど、世界中のかき氷の食べ方が寄せられていますよ。みんな、面白いコンテンツを求めてインターネットを旅しているんです。
—pingmagはブログ形式を取っていますが、ブログについてはどう思いますか?
Webデザイナーになるなら、まずブログを立ち上げるべきです。自分でブログを作って、書いたほうがいい。何かテーマを絞ってね。そうして、スキルを磨きながら、人とのつながりを作るんですよ。ただしデザイナーブログの場合、マイ・ペットとマイ・ミールはダメです(笑)。
ああ、誤解しないで下さい。マイ・ペットとマイ・ミールのブログは全部ダメ、と言っているわけではないです。よく、「ブログの大半はゴミ。読みたくないブログばかりだ」という方がいますが、それでいいじゃないですか。全部のブログが、皆に読まれるものを目指す必要はありませんよ。仲間だけが読みたいコンテンツも、立派なコンテンツでしょ。プライベートなブログがたくさんあるほうが、健全な状態だと思います。
WEB2.0って、インターネット初期に
「こんなことができるかも!」と想像していたこと。
—では、ブログに限らず、今のインターネットの状況は、どう思いますか?
webのはじまりの頃から関わっていた人はみんな感じていると思いますが、webの世界は、一回りしたような印象があります。はじめてインターネットに触った時、私は電話回線の「ピーグルグルグル」に、とってもコーフンしました。「お〜、つながったよー、スゲー!」ってね。その後、Flashのような技術やユーザビリティ議論が発展して、しばらくは『Web上での表現』のほうに興味が集まった。でも、最近また、「お〜、つながったよー、スゲー!」がやっぱり面白いんだな、とみんなが思い直しています。それがWeb2.0ですよ。ただ、初期と違うのは、技術がものすごく進化したこと。昔は、「こんなことができるかも!」って思うだけだったことが、今、本当に実現されてきているわけです。
技術は大事。でも、技術そのものはつまらない。
—技術のお話しが出ました。Webデザインは他のメディア以上に、
技術の進歩と切り離せないところがありますが、トムさんは、Web技術をどうお考えですか?
そうですね。技術は、やはり大事です。最新技術をキャッチアップして、先頭を走りたいと私もいつも思っています。ただ、技術そのものはたいしておもしろくない。これは勘違いしないほうがいいですね。技術を駆使すれば面白いものができあがる、というのは完璧な間違いです。さっきも言った通り、本当にみんなが見たいのは、面白いコンテンツ。それを忘れてはいけないと思います。例えば、私が今関わっている「21_21_DESIGN SIGHT」では、『21_21』マークがepsデータでダウンロ—ドできるようになっています。そのマークをいろんな画像に貼り付けて、自由に遊べる。そして、それをアップロードできる場も、フリッカー内に用意しました。自分でコンテンツを作り、みんなでそのコンテンツを楽しめるしくみになっています。これからは、こういう工夫も、技術と一緒にもっと発達させないといけないでしょうね。
例えば、中華料理屋の「ネチョッ」を、
どうやって一瞬でみんなの心をつかめる表現にするか。
—やっと本題に入りますが(笑)、1-click Awardの審査員として、
応募作品に期待することは何でしょうか?
結局、おもしろいのはインターネット・メディアや技術よりも、人だということを忘れないでほしいです。はやりのデザインや技術からじゃなくて、全然別のところにある「人間の面白さ」から表現を探したほうがいい。例えば、おいしい中華料理屋に限って、店中が油でネチョっとしてたりするでしょ。味もそうだけど、あの「ネチョッ」も忘れられなかったりする(笑)。あれがWebで上手に表現できたら、けっこう面白いと思います。ここで言っちゃったから、もう作品のアイデアには使えませんけど(笑)。こんな風に、おもしろいネタは日常に隠れてるものです。あとは、一瞬の勝負ですから、シンプルに核心をつかまなくちゃいけない。けっこう難しいけど、頑張って下さい。
—ありがとうございました。
では、最後に一言、Webデザインを志す人にアドバイスをお願いします。
繰り返しになりますが、しっかり技術を身につけること。ブログを作って、つながりを作ること。それから、日々の生活を楽しんで、モノを見たり聞いたり話したりする中で、人の面白い部分をたくさん発見すること。自分の気持ちいい、気持ち悪いという感覚を深めて、大事にすること。これらのことに気をつけて、人のマネをせず、とにかくたくさんものを作れば、きっと自然にうまくなります。1-click Awardみたいに、「心を動かすコミュニケーション」という面からインタラクティブ作品を審査するコンテストはあまりないですから、自分を試す絶好のチャンスだと思って、チャレンジしてもらえるといいんじゃないでしょうか。
